1. はじめに|「実がスカスカ」「育ってるのに収穫できない」その原因とは?

とうもろこし栽培でよくある悩みのひとつが、「見た目はしっかり育っているのに、いざ収穫してみると実が入っていない」「穂先がスカスカで、商品にならなかった」といった“実入り不良”の問題です。
とくに営農レベルで栽培している農家にとっては、見た目の良さと中身の差に気づかず、出荷段階でロスが発生するケースも少なくありません。
「苗は順調に立ち上がった」「草丈も十分」「病害虫もなかった」――それでも実が入らないのは、栽培工程のどこかに“見落とし”があるサインです。
本記事では、こうしたとうもろこし栽培における代表的な失敗例とその原因、実践的な対策法を体系的に解説します。
特に「実が入らない」「実が小さい」「曲がっている」といった症状を中心に、受粉、施肥、水管理、環境ストレスなどの観点から原因を掘り下げ、次作につながるヒントをお届けします。
「同じ失敗を繰り返さない」ために、一度立ち止まって振り返ること。
それが、とうもろこし栽培の安定化と収量向上の第一歩です。
2. とうもろこし栽培の基本|実ができる仕組みをおさらい
とうもろこしは、風媒花(ふうばいか)=風によって受粉する作物です。
この特性を理解していないと、見た目はしっかり育っていても、中身がスカスカな実になってしまう原因を見逃してしまいます。
まずは、とうもろこしがどのように実をつけるのか、その基本的な仕組みを確認しましょう。
2-1. 雄穂と雌穂、それぞれの役割
とうもろこしの花は、1株の中に「雄花(雄穂)」と「雌花(雌穂)」がそれぞれ分かれてついています。
- 雄穂(おすい): 草丈の一番高い位置に出てくる花房。ここから大量の花粉が出る。
- 雌穂(めすい): 茎の途中にできる穂の先端から“ひげ”のように出る絹糸(けんし)が雌しべにあたる。
この絹糸1本1本が、将来実になる粒1つ1つと直結しており、花粉がそれぞれの絹糸に届くことで初めて受粉が成立します。
つまり、絹糸に花粉が届かない部分は、実が育たずスカスカになるというわけです。
2-2. 受粉のタイミングとリスク
雄穂が花粉を出すのは、主に早朝~午前中の時間帯。
一方、雌穂が受粉できるのは、絹糸が出てから数日間程度。
この間に、風で花粉が運ばれて絹糸に付着すれば、実がしっかり入ります。
しかし実際の栽培現場では、以下のような要因で受粉不良が起こることがあります:
- 雄穂と雌穂の開花タイミングがずれる(高温・低温ストレス)
- 無風・強風・雨など、花粉が飛びにくい天候条件
- 株間が広すぎて花粉がうまく届かない
- 小面積や家庭菜園などで人工受粉を行っていない
こうした条件を理解せずにいると、「なんで実が入らないのか?」という問題の本質を見落としてしまうのです。
2-3. 1株1穂が基本|着果数と品質のバランス
とうもろこしは、1株に複数の雌穂が出ることがありますが、基本的には1株につき1本の雌穂(第1雌穂)のみを育てるのが原則です。
それ以上を育てようとすると、栄養分が分散し、どの実も中途半端になる可能性が高まります。
品質の良いとうもろこしを安定して収穫するには、
- 受粉成功率を高める栽培設計
- 1穂集中管理による栄養の最適配分
この2点を意識した管理が欠かせません。
受粉の仕組みと環境の影響を理解しておくことで、「なぜ実が入らないのか」という疑問に対する視野が一気に広がります。
3. よくある栽培失敗①|受粉不足で実がスカスカに
とうもろこし栽培で最もよくあるトラブルのひとつが、「実がスカスカで商品にならない」=受粉不良による実入り不足です。
見た目には立派な穂がついているのに、中を開けてみると先端に実が入っていなかったり、全体的に粒の並びが不揃いだったり――これは多くの場合、開花期にうまく受粉が行われなかったことが原因です。
症状の特徴
- 穂先(先端)に実が入っていない
- 粒の並びがバラバラで不ぞろい
- 全体的に実が詰まっておらず、スカスカ
- 複数株で同様の症状が見られる
こうした状態では、いくら見た目が良くても商品としては出荷しづらく、収量ロスや品質低下に直結する重要な問題です。
原因① 株間・条間が広すぎる
とうもろこしは風による受粉を前提とした作物です。そのため、風で花粉が雌穂の絹糸に届くような“密度と配置”が非常に重要です。
株間・条間を広げすぎると、風の通り道にムラができてしまい、近くの株に花粉が届かなくなる=受粉率が下がるという事態が発生します。
📌 対策:
・株間25〜30cm、条間60〜70cmを基本に、ブロック状(4列以上)で密植することで受粉率が安定
・1〜2列だけの細長い作付けは避ける
原因② 天候不良(高温・無風・雨)
花粉は非常に軽く、乾燥した状態で風に乗って飛散します。ところが、
- 無風状態が続いた
- 雨が降って花粉が流れた
- 異常高温で花粉の活性が低下した
などの天候要因が重なると、絹糸に十分な花粉が届かず、受粉不良が起こります。
📌 対策:
・開花期(雄穂・雌穂の出穂)を避けるように播種時期を調整
・夕立が多い時期を避け、天候が安定する時期にピークを合わせる
原因③ 人工受粉を行っていない(小面積・家庭菜園で多い)
少量栽培や家庭菜園の場合、自然受粉だけに頼ると花粉が不足しやすく、受粉ムラが出やすいのが実情です。
📌 対策:
・開花期(雄穂の花粉が出ている朝)に、雄穂を切り取って雌穂の絹糸に振りかける人工授粉を行う
・雄穂を軽く揺らすだけでも花粉が飛散し、受粉率が向上する
補足:雄穂と雌穂の開花タイミングずれ
高温や低温によって、雄穂の開花と雌穂の絹糸の出現がずれると、タイミングが合わず受粉できないことがあります。
📌 対策:
・品種特性と地域の気象データをもとに最適な播種タイミングを選ぶ
・生育ムラが出にくいよう育苗・定植・潅水のばらつきを抑える
受粉不良は、「気づいたときにはもう手遅れ」ということも少なくありません。だからこそ、受粉環境をつくる“事前の設計”が収量確保の鍵になります。

4. よくある栽培失敗②|栄養不足・肥料設計のズレ
受粉が順調に進んでいても、実が太らない、粒が小さい、先端まで育たない…といった症状が出ることがあります。
その原因の多くは、肥料の量や与えるタイミングが適切でなかったことによる「栄養不足」や「肥料設計のズレ」です。
とうもろこしは生育スピードが速く、短期間に多くの栄養を必要とする作物です。だからこそ、どのタイミングで何を与えるかが非常に重要になります。
症状の特徴
- 実が膨らまず、穂先が細くしぼむ
- 粒が小さく、未成熟のまま
- 茎は伸びているのに、穂が育たない
- 葉が黄緑色で全体的に元気がない
こうした症状は、「栄養は足りているつもりだったが、実際には不足していた」ケースが多く見られます。
原因① 元肥が足りない・効いていない
元肥は、作物全体の初期生育と根張りを支える重要な工程です。
ここで栄養が不足すると、その後の成長に弾みがつかず、結果的に穂の充実度が下がります。
📌 対策:
・元肥は窒素(N)・リン酸(P)・カリ(K)をバランス良く施用(目安:10aあたりN8〜10kg程度)
・定植2週間前には施肥を済ませ、しっかり土になじませておく
・有機質と化成肥料を併用して、初期〜中期の栄養供給に対応

原因② 追肥のタイミングが遅い・少ない
とうもろこしは、草丈30cmを超えた頃から急激に養分を必要とする「第二成長期」に入ります。
この時期に追肥が足りないと、穂が十分に肥大せず、結果的に実入り不良に繋がります。
📌 対策:
・1回目追肥:草丈30〜40cm時に窒素主体の追肥を株元に施す
・2回目追肥:雄穂が出始めたタイミング(出穂期)に、窒素とカリを中心に補給
・根に直接かからないよう、株間・条間に施して軽く土寄せ
原因③ 土壌条件とのミスマッチ
肥料そのものは適切でも、土壌のpHや排水性が悪く、栄養がうまく吸収されていないケースもあります。
とくに酸性土壌では、リン酸やカリウムの吸収効率が落ちやすくなります。
📌 対策:
・土壌診断を活用して、pH6.0〜6.5前後に矯正(苦土石灰など)
・排水不良の圃場では高畝や暗渠排水で根の健全性を確保
・微量要素(マグネシウム、ホウ素など)も必要に応じて補給

家庭菜園での注意点
家庭菜園では、つい「肥料は少なめが安全」と考えがちですが、とうもろこしはある程度しっかり栄養を与えないと結果が出にくい作物です。
また、プランターや鉢栽培では肥料分の流亡が早いため、追肥の回数を増やす工夫が必要になります。
とうもろこしの肥料管理は、単に“与える”だけでなく、「タイミング」と「生育段階に応じた設計」が成否を大きく分けます。
“ちょっと足りなかった”が、収穫量に大きな差を生む作物だからこそ、土づくりと計画的な施肥設計が重要です。
5. よくある栽培失敗③|過密・過剰着果による栄養分散
「とうもろこしの穂はたくさん出たのに、どれも育ちきらなかった」
「実が小さいままで終わってしまった」
――そんな経験がある方は、“栄養の分散”による失敗を疑ってみる必要があります。
とうもろこしは見た目以上に栄養要求が高い作物であり、1株の中で競合が起こると、どの穂も育ちきらないという結果を招きがちです。特に栽植密度や着果数の管理を誤ると、実入りに大きな差が出てしまいます。
症状の特徴
- 穂が複数出ているが、どれも細くて短い
- 粒が不ぞろいで、実の詰まりが悪い
- 見た目には元気だが、収穫してみると不十分な実ばかり
- 隣の株と比べて生育にムラがある
これらはすべて、過密栽培による競争や、1株に複数穂がついたまま放置したことによる栄養分散が原因である可能性が高いです。
原因① 株間が狭すぎて光や養分が競合
とうもろこしは直立性で密植できる作物ですが、密度が高すぎると、日照・水分・養分の取り合いが発生します。
結果的に、どの株も中途半端に育ってしまい、草丈がそろわない・実入りがバラつくという事態になります。
📌 対策:
・株間25〜30cm、条間60〜70cmを守る
・風通しと日当たりを考慮した「ブロック栽培」が理想
・土壌が肥沃な圃場でも詰めすぎは禁物
原因② 複数穂を残したままにしている
とうもろこしは1株に複数の雌穂(実の元)がつくことがありますが、基本的には第1雌穂(最初に出てきたもの)だけを育て、他は早めに除去するのが鉄則です。
複数穂を残すと、栄養が分散し、どれも十分に太らないまま終わってしまうケースが多くなります。
📌 対策:
・草丈が50〜60cm程度に伸びた時点で、第1雌穂以外を除去する
・余計な穂を育てないことで、1本の実に栄養を集中させる
特に家庭菜園では「もったいないから」と複数残してしまうケースが多いですが、結果的にすべての実が不完全になるので、早めの見極めが重要です。
原因③ 生育ムラによる個体差
種まきの深さや発芽不良などで生育に差が出ると、強い株が周囲の栄養を吸い取り、弱い株が育ちにくくなるという現象も起こります。
📌 対策:
・均一な播種・水分管理で発芽を揃える
・極端に小さい苗や発芽不良株は早期に間引く判断も必要
とうもろこしは「1株1穂」が基本。
“多く実らせる”よりも、“1本を確実に太らせる”方が、結果的に収量も品質も安定します。
栄養の集中=実入りの良さに直結するため、栽植密度と着果数の管理は、収穫時の満足度を大きく左右するポイントです。
6. よくある栽培失敗④|気象ストレスとその回避策
とうもろこしは比較的強健な作物とされていますが、気象条件が悪化すると実入りや品質に大きな影響を受ける作物でもあります。
特に露地栽培では、高温・乾燥・長雨・強風・急激な気温変化など、自然環境からのストレスをどう防ぐかが、安定生産の鍵になります。
ここでは、気象ストレスによって引き起こされる典型的な栽培トラブルと、その具体的な対策を紹介します。
症状の特徴
- 実が曲がる・途中で変形する
- 絹糸がうまく伸びず、受粉が不完全になる
- 果実の肥大が止まり、穂先が育たない
- 茎が折れる・倒伏する
- 実入りや粒ぞろいがバラバラになる
いずれも、植物体がうまく対応できなかったことによる“生育障害”であり、品種や施肥だけでは補えない部分です。
原因① 高温・乾燥によるストレス
とうもろこしは暑さにある程度強い作物ですが、気温が35℃を超えるような高温が続くと、花粉の活性が落ち、受粉不良が起こりやすくなります。
また、乾燥が進むと絹糸の伸長も悪くなり、さらに受粉率が低下します。
📌 対策:
・播種時期を調整して、開花期を極端な高温時期と重ねない
・マルチや敷きわらで土壌の乾燥を防ぎ、地温の急上昇を緩和
・乾燥が続く時は、朝または夕方に十分なかん水を行う(特に開花前後)
原因② 長雨・過湿による根傷み・病害
長雨が続くと、根が酸欠を起こして栄養吸収が落ちたり、根腐れ・立ち枯れの原因になる病気が発生することがあります。特に低地や排水の悪い圃場では、こうした症状が顕著です。
📌 対策:
・播種・定植前に排水性を確保(高畝・暗渠・明渠など)
・雨よけ資材(簡易ビニールトンネルなど)の活用も選択肢
・長雨が予想される時期の播種は避け、天候を見て作型をずらす
原因③ 強風による倒伏・受粉不良
台風や突風によってとうもろこしが倒伏すると、受粉不良や生育停止、果実の変形につながることがあります。とくに草丈が伸びきる出穂期以降は倒れやすく、対策が欠かせません。
📌 対策:
・防風ネット・風よけ資材を設置する(特に圃場の端)
・生育中期に土寄せして株元を安定させる
・株間を詰めすぎないことで、風の通り道を確保
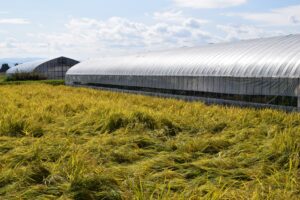
原因④ 急激な気温差
日中と夜間の気温差が大きすぎると、絹糸の伸びや花粉の活性に影響が出て、受粉率が不安定になります。
このような気象条件は、標高が高い地域や春播きの早期作型で起きやすくなります。
📌 対策:
・標高や気候帯に合った作型・品種を選定する
・播種を少し遅らせて、開花期を安定した時期に合わせる
・必要に応じて簡易トンネルで初期の保温・防寒対策
とうもろこし栽培は、土・肥料・栽培技術といった“人の手”による管理だけでなく、“自然の機嫌”にどう付き合うかも大切なポイントです。
事前に想定し、適切な対策を講じておくことで、天候のブレに強い安定生産体制が整っていきます。
7. よくある栽培失敗⑤|病害虫・鳥獣害の見落とし
とうもろこしの栽培で油断しがちなのが、**収穫直前になってからの「予想外の被害」**です。
穂がしっかり育ってきたと思った矢先、穂先が食われていたり、実の中に虫が入っていたり、収穫目前で台無しになるケースは少なくありません。
こうした病害虫や鳥獣害の見落としは、手間をかけた分の損失が大きく、心理的ダメージも大きい失敗のひとつ。
ここでは、とうもろこし栽培でよく見られる主な加害者と、その実践的な対策を解説します。
7-1. 症状の特徴
- 穂先や果皮が食べられている
- 実の中に虫やフンが混入している
- 芯が腐ったり、発育が途中で止まっている
- 被害株が点在して広がる傾向がある
7-2. 主な加害要因と対策
① アワノメイガ(害虫)

被害内容: 穂先や茎の内部に侵入し、実や芯を食害。フンが混ざり、実が商品にならなくなる。
発生時期: 6月〜8月(年2〜3化)
発見のポイント: 穂先に穴、フン、枯れ込みが見られる。
📌 対策:
・出穂期前後に適期で防除(BT剤や登録農薬)を散布
・穂先にテープや防虫ネットをかぶせる方法も家庭菜園では有効
・発生初期の見回りと早期対処がカギ
② すす紋病・灰色かび病などの病気

被害内容: 穂や葉に黒いすす状のカビ、灰色の腐敗など。湿度が高いと発生しやすい。
原因: 長雨・風通し不良・肥料過多・連作など
📌 対策:
・輪作(1〜2年空ける)と土壌改良で土の健全化
・雨が多い時期は防除資材(銅剤・灰色かび対応薬剤)を予防的に散布
・通気性を保つために適切な株間と葉の整理を行う
③ カラス・ハクビシンなどの鳥獣害

被害内容: 実の成熟直前に食べられる/穂が引きちぎられて地面に落ちている
発生タイミング: 甘みが増す収穫期直前が最も多い
📌 対策:
・ネットやテグスを圃場全体に張る(特に周囲)
・夜間の対策には電気柵やセンサーライトも有効
・人の気配が必要な場所ではラジオや音声装置の活用も効果あり
・穂をひとつずつ紙袋で包む「袋かけ」も家庭規模なら有効

④ ネキリムシ・ヨトウムシなどの土中害虫

被害内容: 幼苗が地際から切られる/生育途中で突然枯死する
発生タイミング: 初期(播種後〜本葉期)
📌 対策:
・播種・定植前に殺虫剤または忌避資材を混和処理
・周囲の雑草をこまめに除去し、害虫の温床を減らす
・発芽期はこまめに見回って被害苗を早期補植

7-3. 定期的な見回りが最大の防除策
とうもろこしは生育が早く、害が出始めてからでは防除が間に合わないことも多い作物です。
だからこそ、開花期〜収穫期は毎日見回るくらいの意識で圃場を観察し、早期発見・早期対処を徹底しましょう。
特に「今年は大丈夫そうだな」と感じたときほど油断は禁物。
数日で一気に被害が広がることもあるため、こまめなチェックと早めの処置がリスク回避の基本です。
8. まとめ|失敗から逆算すれば、次はうまくいく
とうもろこし栽培における「実が入らない」「育ったのに収穫できない」といった失敗は、一見不可解に思えても、一つひとつ原因をたどっていけば、必ず改善のヒントがあります。
受粉のタイミング、施肥の量と時期、株間の調整、間引きの判断、気象ストレスへの備え、病害虫や鳥獣害の早期対処――どれか一つでも欠ければ、期待していた実りにはつながりません。
ですが、それぞれの失敗は「うまく育てるために必要な“経験値”」でもあります。
とうもろこしは生育が早く、栽培の流れが明確な作物です。だからこそ、一度の失敗をきちんと分析して対策すれば、翌年には成果として返ってきやすいという特長もあります。
「なぜ失敗したのか」をしっかり振り返ることが、次の成功への最短ルートです。
栽培の工夫と観察力を積み重ねながら、次こそ“ずっしり詰まった実”を手にできることを願っています。










